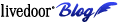2013年11月22日
純粋培養したから無垢無罪ってわけじゃない
ここからのつづき。
プロジェクト的にテレビアニメも組み込まれてるらしい。劇場版実写前後編にテレビアニメってDEATH NOTE彷彿の展開だな(なお、あれは実写版が、原作ファンも納得どころか言わば原作/アニメ超えした稀有な例)。
半年〜一年は使わないとだな。問題は表現寄生いや規制か…で、その点については劇場映画に本来は分があるんだけど、製作側が自主規制するだろうな、集客(万人受け)を考慮して。そこらへんは仕方がないのかな…そういうとこ思い切って突き抜けてもらいたいもんだが…無理なんだろうなあ。
「残酷描写無しでもテーマは伝えられる」、勿論それもわかるんだけど、ならば「キチンと作れば残酷描写があろうとも伝わるはず(それが障害・問題ではなくなる)」って考え方というか取り組み方も、してほしいんだよね。
「それありき」で成立するジャンル・方法論とはまた違う、「それがあるからこそ、より活きる(生きる)」作り方。たとえば『プライベートライアン』ってそれだったと思う、『戦場のピアニスト』や『火垂るの墓』もそう(もちろん高畑版)。
まさしく『寄生獣』も、そういう作品だと思う。
いつまでも口当たりのいい表現ばかりでは、観客も刮目・覚醒、「成長」しないんじゃないかな。そこらへんに今のメジャー系邦画作品の弱さ、悪しき循環の病理があると俺は思っている。ずっと安易な「感動」の応酬で生き長らえるつもりなんだろうか。「美しい(やさしい)死」ばかりなんてのは、かえって「人の命が軽く扱われて」いないだろうか?
(余談だけど、邦楽/リスナーの多くが、耳ざわりのいい"言葉"を語る/聴くばかりになってしまったのとも、似てるかもね。)
死とは時に唐突で、なんの説明もなく、感傷に浸る暇すら与えてはくれない、理不尽で残酷なものなのだ。いともたやすく壊れ/終わってしまうからこそ「生」の有り様、他者の存在が重く深く伝わることもある。
ちなみに、岩明均氏の描く「死」のあっけなさ、「死体」の恐ろしさ(抜け殻感)、その秀逸な「無」の表現は、ポール・バーホーヴェン監督の手腕と相通じるものがあると俺は思っているのだが、いかがだろうか?
この際だからもう一つ言うと、富野由悠季御大も残酷だよね。およそ死の瞬間に「泣ける」なんて隙を与えてはくれない、「えっ」て感じで終わってる。そして後から「そうだ、もういないんだ…」ってのが不意に襲ってくる。直接的に死を形として見せる(遺体を見せる)ことは逆に殆どないけど、残酷。そういう手法も、またある。
あ、激しく脱線してしまった(・ω・)すまぬ。
なお、実写・アニメいずれも時代設定、それに伴う様々な風俗背景についての適宜変更は、まあ容認したい。…本当は、あのファッションまで再現してもらいたいけどね(笑)あれ、物語とリンクした含みあるし。なお、その手法をリスペクトしていたのが『けいおん!』の唯T(かもしれない←
【蛇足】
これ書いた日の夜テレビ点けたら『火垂るの墓』やってた、ついさっきのことだ、どえらい不意打ちだった(´;ω;`)ああもう…
プロジェクト的にテレビアニメも組み込まれてるらしい。劇場版実写前後編にテレビアニメってDEATH NOTE彷彿の展開だな(なお、あれは実写版が、原作ファンも納得どころか言わば原作/アニメ超えした稀有な例)。
半年〜一年は使わないとだな。問題は表現寄生いや規制か…で、その点については劇場映画に本来は分があるんだけど、製作側が自主規制するだろうな、集客(万人受け)を考慮して。そこらへんは仕方がないのかな…そういうとこ思い切って突き抜けてもらいたいもんだが…無理なんだろうなあ。
「残酷描写無しでもテーマは伝えられる」、勿論それもわかるんだけど、ならば「キチンと作れば残酷描写があろうとも伝わるはず(それが障害・問題ではなくなる)」って考え方というか取り組み方も、してほしいんだよね。
「それありき」で成立するジャンル・方法論とはまた違う、「それがあるからこそ、より活きる(生きる)」作り方。たとえば『プライベートライアン』ってそれだったと思う、『戦場のピアニスト』や『火垂るの墓』もそう(もちろん高畑版)。
まさしく『寄生獣』も、そういう作品だと思う。
いつまでも口当たりのいい表現ばかりでは、観客も刮目・覚醒、「成長」しないんじゃないかな。そこらへんに今のメジャー系邦画作品の弱さ、悪しき循環の病理があると俺は思っている。ずっと安易な「感動」の応酬で生き長らえるつもりなんだろうか。「美しい(やさしい)死」ばかりなんてのは、かえって「人の命が軽く扱われて」いないだろうか?
(余談だけど、邦楽/リスナーの多くが、耳ざわりのいい"言葉"を語る/聴くばかりになってしまったのとも、似てるかもね。)
死とは時に唐突で、なんの説明もなく、感傷に浸る暇すら与えてはくれない、理不尽で残酷なものなのだ。いともたやすく壊れ/終わってしまうからこそ「生」の有り様、他者の存在が重く深く伝わることもある。
ちなみに、岩明均氏の描く「死」のあっけなさ、「死体」の恐ろしさ(抜け殻感)、その秀逸な「無」の表現は、ポール・バーホーヴェン監督の手腕と相通じるものがあると俺は思っているのだが、いかがだろうか?
この際だからもう一つ言うと、富野由悠季御大も残酷だよね。およそ死の瞬間に「泣ける」なんて隙を与えてはくれない、「えっ」て感じで終わってる。そして後から「そうだ、もういないんだ…」ってのが不意に襲ってくる。直接的に死を形として見せる(遺体を見せる)ことは逆に殆どないけど、残酷。そういう手法も、またある。
あ、激しく脱線してしまった(・ω・)すまぬ。
なお、実写・アニメいずれも時代設定、それに伴う様々な風俗背景についての適宜変更は、まあ容認したい。…本当は、あのファッションまで再現してもらいたいけどね(笑)あれ、物語とリンクした含みあるし。なお、その手法をリスペクトしていたのが『けいおん!』の唯T(かもしれない←
【蛇足】
これ書いた日の夜テレビ点けたら『火垂るの墓』やってた、ついさっきのことだ、どえらい不意打ちだった(´;ω;`)ああもう…
ed209 at 10:17│clip!│G+不定期まとめ(抜粋)